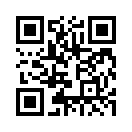2014年09月21日
城下町土浦
土浦地方には、今から7,8千年前に人が住みついたと言われている。
町の中心にある土浦城は15世紀初頭に若泉三郎によって築かれ、江戸初期に藤井松平氏時代に土浦城の内外の整備が開始されたという。
城下町として体裁が整ったのは江戸中期ごろと言われている。
1604年に水戸街道が開通し、商人や職人が移り住むようになり、町屋が設けられたようだ。
また、人の行き交う町として宿場町としての要素も加わり発展していったらしい。
当時は、土浦から江戸まで霞ヶ浦、利根川、江戸川水系を結び、高瀬船などによって物資が輸送されていた。中でも醤油醸造業は盛んで、亀甲大(キッコウダイ)の商標で江戸城御用にも指定され、野田や銚子と並んで醤油の産地として知られていたという。
今では市内に現存する醤油醸造業者は柴沼醤油のみとなっている。
醤油が「むらさき」と呼ばれるのは、筑波山(別名、紫峰)を望むこの地域が醤油の主産地であったからだと言われている。
(出展:まちかど蔵資料館)
なるほど。
市内のスーパーに並んでいる「紫峰」という醤油は柴沼醤油醸造のものだったのか。
歴史を辿っていくと、様々なことが見えてくる。
そういえば、土浦駅から関鉄バスに乗ると、桜橋という停留所があるが、そこが「桜橋」という地名でもないし、不思議に思っていたのだ。
この停留所は、かつて桜橋が架かっていた場所なのだ。
見れば「櫻橋」という石碑があり、橋の名残だったことがうかがえる。
まちかど蔵に展示されている古い写真からも、町中を川が流れていることがわかる。
イタリアでいうところのヴェネツィアを彷彿とさせる景色だ。
古きよき土浦を、もっと知りたいと思うPIPPOであった。

町の中心にある土浦城は15世紀初頭に若泉三郎によって築かれ、江戸初期に藤井松平氏時代に土浦城の内外の整備が開始されたという。
城下町として体裁が整ったのは江戸中期ごろと言われている。
1604年に水戸街道が開通し、商人や職人が移り住むようになり、町屋が設けられたようだ。
また、人の行き交う町として宿場町としての要素も加わり発展していったらしい。
当時は、土浦から江戸まで霞ヶ浦、利根川、江戸川水系を結び、高瀬船などによって物資が輸送されていた。中でも醤油醸造業は盛んで、亀甲大(キッコウダイ)の商標で江戸城御用にも指定され、野田や銚子と並んで醤油の産地として知られていたという。
今では市内に現存する醤油醸造業者は柴沼醤油のみとなっている。
醤油が「むらさき」と呼ばれるのは、筑波山(別名、紫峰)を望むこの地域が醤油の主産地であったからだと言われている。
(出展:まちかど蔵資料館)
なるほど。
市内のスーパーに並んでいる「紫峰」という醤油は柴沼醤油醸造のものだったのか。
歴史を辿っていくと、様々なことが見えてくる。
そういえば、土浦駅から関鉄バスに乗ると、桜橋という停留所があるが、そこが「桜橋」という地名でもないし、不思議に思っていたのだ。
この停留所は、かつて桜橋が架かっていた場所なのだ。
見れば「櫻橋」という石碑があり、橋の名残だったことがうかがえる。
まちかど蔵に展示されている古い写真からも、町中を川が流れていることがわかる。
イタリアでいうところのヴェネツィアを彷彿とさせる景色だ。
古きよき土浦を、もっと知りたいと思うPIPPOであった。

Posted by pippo at 21:29│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
コメントフォーム